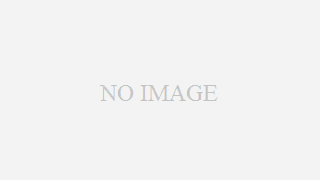 コラム
コラム プラネタリウムの社会的役割の変化:教育、娯楽、観光資源として
はじめにプラネタリウムは、かつて「星空を学ぶ教育装置」というイメージが強かったですが、現在では「総合的な娯楽施設」「地域観光の目玉」としても認識されるようになりました。時代の変化に合わせて、プラネタリウムが担う社会的役割も多様化しており、そ...
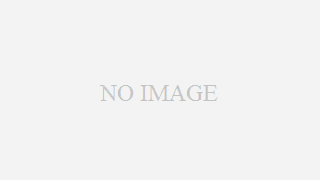 コラム
コラム 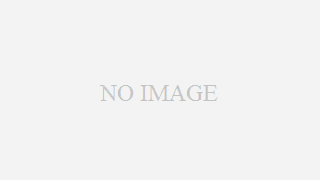 コラム
コラム 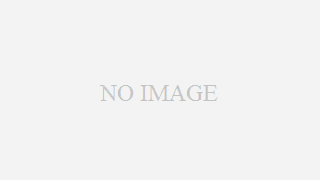 コラム
コラム 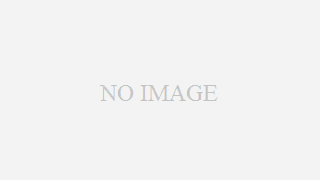 コラム
コラム 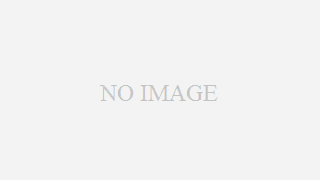 コラム
コラム 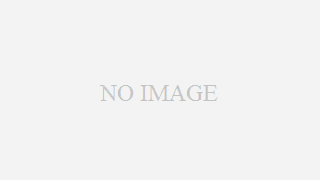 コラム
コラム 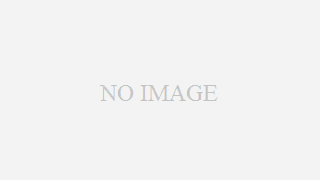 コラム
コラム 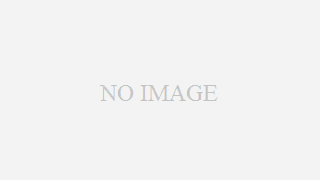 コラム
コラム 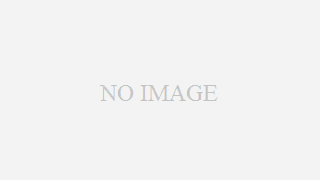 コラム
コラム 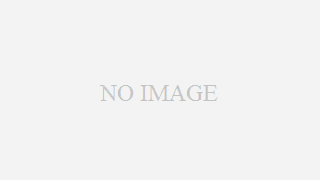 コラム
コラム